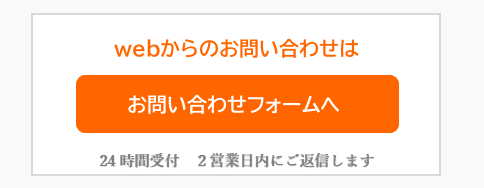事業を拡大するには、新たな企業との取引を積極的に行っていく必要がありますが、 そのときに不安になるのが「相手の信用力」です。
創業したばかりの会社などは当然ですが、それ以外でも取込み詐欺や計画倒産などを狙っているケースもあるため、取引の開始にあたっては十分な注意が必要です。
ここでは信用調査会社などを使わずに、自分でできる取引先の調査方法や、万が一の場合を想定した対策の方法についてご説明します。
この記事で書かれたことを行っていただければ、相手の信用力を見抜けるようになるだけでなく、取引上のリスクを大きく減らせるようになります。
なぜ、事前に取引先の調査が必要なのか?
新規の会社と取引をする場合に、なぜ事前に調査する必要があるのかといえば、それは以下の理由によります。
代金を回収する前に倒産してしまう可能性がある
中小企業では資金繰りがうまく行かず、自転車営業となっているところが少なくありません。
とくに創業したばかりの会社は、 財務体質が脆弱で、 営業事態もうまくいっていないケースが少なくありません。
そのため、このような会社とはじめから大きな取引をしてしまうと、 代金の回収ができなくなってしまう可能性が高くなります。
取込み詐欺や計画倒産を狙っている可能性がある
企業の中には、はじめから取込み詐欺や計画倒産をもくろんで、取引を持ちかけてくるところもあります。
取込み詐欺は、代金を支払うつもりがないのに掛取引を持ち掛け、そのまま逃げてしまう手口であり、計画倒産は、代金を支払わずに会社を法的に倒産させてしまう手口です。
いずれにしても、はじめから支払いを免れるために計画的に行われていることから、一度被害にあってしまうと代金の回収はかなり難しくなってしまいます。
そのため、このような悪質な企業に引っかかってしまうと、大きな損失を被るだけでなく、連鎖倒産の引き金となってしまいます。
トラブルがあった時に回収が困難となる
売掛けなどの信用取引をしたときには、相手とのトラブルが発生したり、相手の財務状況が急激に悪化すると、代金の回収が非常に困難となります。
もちろん裁判をすれば、その正当性を証明することができますが、仮に勝訴判決をもらっても代金の回収ができるとは限りません。
というよりは、通常、そのような企業から全額の代金の回収をすることは、ほぼ不可能となります。
はじめて取引をする企業にはこのようなリスクがあるため、
● 事前にその企業の信用状況を調査すること
● いきなり大きな金額の取引や売掛取引をしないこと
● 被害にあった時のリスク対策をしておくこと
の3点について対策することが取引の安全のために重要となります。
自分で行う調査の方法
はじめて取引をする場合や、つきあいの浅い会社と取引をする場合には、あらかじめ相手の会社の信用状況を調査してから行うべきです。
信用調査の方法には、専門会社に依頼するやり方もありますが、コストがかかるため日常の取引では現実的でないケースもあります。
しかし、そんな場合でも、自社でできる範囲で相手の調査をしておくことは、安全な取引のため最低限行うべき対策といえます。
具体的には、次のようなことをするだけでも、かなりの情報を集めることができるので、ぜひ実践することをお勧めします。
会社の登記簿謄本または開業届を確認する
取引相手が法人の場合、まずはじめに行うべきなのが「会社登記簿謄本の確認」です。
どんな種類の法人であっても、必ず会社の登記簿が作られるので、もし登記がされていない、会社登記簿を提出できないような場合には、詐欺の可能性が考えられます。
中には「現在、登記手続き中だ」などとごまかそうとするケースもありますが、その場合には、登記簿ができるまでは取引や契約をしないようにしましょう。
相手が個人事業主の場合には登記簿謄本はありませんが、その場合には税務署へ開業届の提出をしているはずですのでこれを提出させて確認します。
この際のポイントは、開業届に税務署の受付印が押されているかどうかを確認することです。
税務署の受付印が押されていないものは、何の証明にならないだけでなく、本当は届出をしていない可能性があるため、シッカリと確認ができない場合には取引をしないようにします。
相手の会社のホームページを確認する
最近では、ほとんどの会社でホームページを作っているのが当たり前となっています。
中には、「できたばかりの会社なので、まだ、ホームページを作っていない」とか「ホームページでの営業をしていない」などのケースもありますが、ある程度社歴があるにもかかわらずホームページがない場合には、疑ってみた方がよいでしょう。
ホームページがある場合は、 そこに記載されている会社概要と登記簿謄本の内容(本店所在地や役員など)に相違がないかを確認しておく必要があります。
具体的には、次の点に注意して確認します。
| ● いつできた会社なのか?(「会社設立念月日」で確認) -極端に社歴が短い場合は要注意 ● どのようなことをしている会社なのか?(「目的欄」で確認) -やたらと多くの事業目的を登記している、風俗営業をしている場合には要注意 ● 資本金額はどのくらいか?(「資本金欄」で確認) -極端に資本金額が少ない場合には、少しの資金繰り悪化で倒産してしまう可能性大。 ● 会社の本店や代表者の住所はどこか?(「本店欄」、「役員欄」で確認) -地図上で建物が見当たらない場合や、レンタルオフィスになっている場合は要注意 ● どこか別の場所から移転してきていないか?(「その他欄」で確認) -どこか別の場所から移転てきている場合には、その他の欄に 「●年●月●日」~から本店移転 と記載されます。 このような会社の中には、他の倒産会社を詐欺に利用する目的で買収しているケースもあるため、そのような会社については要注意 |
なお、仮にホームページがある場合であっても、それが無料ブログや無料サービスで作られているものである場合は、少し気を付けた方がよいでしょう。このような無料で作成できるHPは、詐欺の舞台の材料とて、利用されていることがあります。
会社の代表番号や個人の携帯番号に電話をかけてみる
相手の名刺を取得した場合は、会社の代表番号や代表者の携帯番号に電話をしてみて、本当にその番号が存在するかを確認しておく必要があります。
「何度かけてもでない」、「通話ができない」「会社の人間が出ずに、秘書サービスに転送される」などの場合は、その存在を疑ってかかるべきです。
なお、自分の携帯から連絡をすると履歴が残るから嫌だという方については、公衆電話から確認してみるとよいでしょう。
最近では、その電話番号が詐欺などに利用されていたものかどうかを調べることができるサイトもあるため、このようなサービスを利用するのもおすすめです。
相手の事務所が存在するかを確認する
会社の登記簿謄本に記載されている本店所在地に、本当に事務所が存在するのかを確認してみます。
事務所所在地が遠方の場合には難しいこともありますが、極力、この調査はするべきであり、もし、事務所の実態がない場合には、即座に取引を中止した方がよいといえます。
なお、最近では実態がない会社ついても、本店登記のできるレンタルオフィスなどがありますが、本店がそのような場所になっている場合には、その存在を疑ってかかった方がよいでしょう。
相手が許認可業者の場合は、管轄省庁のホームページで確認する
不動産業のように、営業をするうえで許認可が必要となる会社の場合には、その許認可を管轄する監督官庁のホームページに許認可業者の名簿が掲載されていることがほとんどです。
そのため、相手の業種がこのようなものである場合には、正式な許可を取得しているのかを確認します。
ただし、建設業については、原則、500万円未満の工事は建設業の許可がなくとも行うことができることに注意してください。
会社名や代表者名を「●●社 評判」などのキーワードで検索してみる
会社の正式名称や本店がわかれば、それをネットで検索して、その会社の評判を知ることができます。
もしも、過去にトラブルや事件を起こしている書き込みがある場合には、取引をやめた方がよいでしょう。
検索をしても何の情報も出てこない場合もありますが、その場合には「あまりに規模が小さい会社」または「営業活動をしていない会社」、「最近作られたばかりの会社」などの可能性が考えられますので、状況に応じて取引をすべきかどうかを考えます。
また、その会社の取引先がわかる場合には、こちらについても検索すると、どんな相手と取引をしているのかがわかるため、より多くの情報を手に入れることができます。
取引開始前の注意点
はじめての会社と取引をする場合には、あらかじめ以下の対策をすると、相手の素性の確認や代金を回収する際に役立ちます。
代表者の身分証明書をコピーする
取込み詐欺や計画倒産を考えている人間は、会社の情報を見せることはあっても、自分の個人情報を見せることを極端に嫌がります。なぜなら、このような人間にとってはそれが身元の特定につながるからです。
なので、相手の身分の確認は名刺だけでなく、運転免許証などの公的な証明書を提出させて行うようにします。
その際に、相手が免許証の提示を嫌がるならば、何かよからぬことを企んでいる可能性があると考えた方がよいでしょう。
有名人と撮った写真などは信用しない
よく有名人や政治家と撮った写真を見せて相手を信用させようとするケースがいますが、そのほとんどは単なるパーティーや懇親会の席でお願いして撮ったものです。
したがって、このような写真を見せられた場合でも、うかつに「●●との付き合いがある人」などと考えず、 そのような写真を見せること自体が怪しいと疑ってかかる必要があります。
詐欺の手口を理解しておく
詐欺に引っかからないようにするには、詐欺の手口を知っておくことが効果的です。
最近ではSNSを利用したものや、警察や裁判所、役所などを語った巧妙な手口が増えているため、日ごろからどのような詐欺が流行っているのかや、行政のHPなどで詐欺の手口を知っておくことが重要となります。
金融機関の口座情報を確認しておく
事前の準備で以外と重要なのが、「相手方の金融機関の口座情報の確認」です。
なぜこれが重要かといえば、万が一相手の預金口座を差し押さえる場合には、金融機関名や口座番号などの情報が必要となるからです。
しかし、トラブルになってからは、相手からこれを聞き出すことはほとんど不可能となります。
そのため、事前に取引口座を確認するだけでなく、もし、それが難しい場合には「何らかの名目を付けて少額の振り込みをする」などの理由で、あらかじめ相手の口座情報を入手しておく必要があります。
3回目までは、半額を現金でもらう
はじめての取引の時だけでなく、できれば3回目の取引までは半額を現金でもらうようにしておくと安全です。
なぜなら取り込み詐欺では、相手に信用させるため2回目くらいまでは現金で支払うことが多いからです。
そして3回目以降に大きな取引を売掛けで持ちかけ、そのまま逃げる、倒産する というのが常套手段です。
したがって、3回目ぐらいまでは半金を現金でもらうなどとしておくと、大きな被害に遭いにくくなります。
決算書を提示してもらう
詐欺会社などではどんなに上手く繕っていても、決算書までは作っていないのが普通です。
また、仮にこれを作成していても、たいていは実質的な取引がないことがその内容からわかります。
したがって、「決算の内容が悪いから」などの理由で決算書の提示を渋る場合には、それ以上の取引をしないことをおすすめします。
また、決算書を提示してもらう場合には、貸借対照表と損益計算書だけでなく、 勘定科目明細を含めたすべての資料を提示してもらうようにしてください。
これらの部分には、使用している銀行口座や取引先、借入先などの重要な情報が含まれているため、重要な情報源となります。
保証人や抵当による保全について
大きな取引をする場合や、リスクのある取引をする場合には、保証人や抵当権により債権を保全しておくことも必要となります。しかし、保証人と抵当権はその法的な性質や効果が異なるため、これらを理解した上で活用しないと思わぬ失敗につながります。
保証人の保証について
<保証は必ず連帯保証で行う>
保証人は複雑な手続きが必要なく、書類だけでできる保全手続きです。また、相手にとっても抵当権の設定よりは、比較的、ハードルの低い方法となります。
ただし、保証人を立てるときに注意すべきなのが、「単なる保証人ではなく、必ず連帯保証人とする」ということです。
なぜなら、通常の保証人の場合には「催告の抗弁権」と「検索の抗弁権」という二つの抗弁権があるからです。
「催告の抗弁権」とは、保証人が債権者から保証行為を要求された場合に、まずは債権者に対し催告をすることを求めることができる権利です。とはいえ、普通は債権者への請求をした後に保証人への請求を行うでしょうから、これについてはあまり問題とはならないでしょう。
これに対して、「検索の抗弁権」は保証人が債権者に対し、まず債権者に取り立て可能な財産がないかを検索せよと主張できる権利のため、この抗弁権が主張された場合には、 その分手間がかかることになります。
しかし、連帯保証人には、これらの抗弁権が認められていません。
そのため、保証人を用意してもらうときには必ず、連帯保証人とすることが重要となります。
<保証人の分別の利益に注意>
なお、単純な保証とした場合には、保証人側に分別の利益があることに注意してください。
「分別の利益」とは、複数の保証人が債務を等しい割合で負担することのできる利益をいいます。
たとえば、保証人が2人いて債務者が1,000万円の返済ができなくなった場合、債権者は保証人一人に対して500万円の請求しかすることができません。これに対して連帯保証の場合には、各保証人に対して1,000万円ずつの請求をすることができます。
このように分別の利益は保証人対しては有利に働きますが、債権者側には不利となります。
<保証はアテしすぎない>
相手が法人である場合、会社を債務者、代表者を連帯保証人とするケースがよく見られますが、ケースによってはこの保証が役にたたない場合もあります。
なぜなら、債務者である法人に資力がない場合には、代表者にも資力がなかったり、 他の保証人となっていることがほとんどだからです。
そのため、「十分な保証人が用意できない」、「保証人に問題がありそう」という場合には、保証人がいるからと安心せずに、他の保証人を求める、取引を見送るなども検討すべきといえます。
抵当権の設定について
<抵当権とは>
「保証人が用意できいない」、「保証人の保証力が低い」などの場合には、抵当権の設定も考える必要があります。
抵当権とは、民法で定められた担保物権の一種で 、債務の不履行があった場合には、裁判手続きによらずに、抵当権にもとづいて目的物を差し押さえて売却できる権利です。
抵当権には、次のような特徴があります。
抵当権の主な特徴
| ● 不動産などを担保とすることにより、貸金や売掛金の支払いを保全することができます。 約束した支払いがない場合には、裁判手続きによらず、その目的物を売却することができます。 ● 抵当権の目的となっている建物等が火災などにより消失した場合には、債務者がそれにより受け取る保険金などに対して差し押さえをすることができます。(物上代位) ● 債務者が破産した場合でも、優先的に担保の売却代金から代金の回収をすることができます。(別除権) ● 抵当権の設定をした場合は、その目的である不動産の所有権が第三者に移転しても、その不動産の売却をして代金の回収をすることができます。 |
ただし、抵当権の利用には、次の点に注意が必要です。
| ● 自分より先に登記された抵当権がある場合には、その抵当権が優先して返済をうけます。そのため、 先の順位の抵当権の債権額が大きい場合には、後の順位の抵当権者は配当を受けられない場合があります。 ● 債務者について破産手続きが行われた場合、破産に近い時期に設定された抵当権は、管財人により否認されることがあります。 ● 抵当権の効力を債務者以外の第三者に主張するためには、その目的物について抵当権設定登記をする必要があります。この抵当権設定登記は、債権者と債務者(借主)の共同で行う必要があるため、債務者の協力が得られない場合には登記をすることができません。 ● 抵当権の設定には、一定の登録免許税が必要となります。 ● 抵当権に基づいて不動産を売却する場合には、評価や売却の手数料を建て替える必要があります。 |
抵当権は、これらの特徴を持つため強力な債権の保全手段となりますが、相手方の協力が必要であり、また、各種の手数料がかかります。
保証人や抵当権を依頼するタイミング
代金を安全に回収するには保証人や抵当権の設定が効果的ですが、通常、取引先に対して、保証人を立ててもらうことや、抵当権の設定のお願いするのが難しい場合が多いと思います。
しかし、相手の経営に危険信号が出ているにも関わらず、いつまでも通常の取引を継続していたのでは万が一の場合の損失が膨らむばかりとなります。
そのため、取引状況、自社の資金力などを考え、あらかじめ、取り立てのルールを考えておく必要があります。
たとえば、次のような危険信号が相手が企業に出ている場合には、速やかに保証人や担保の設定を検討した方がよいでしょう。
保証人や抵当権の設定を依頼する時期
| ● 3ヶ月内に2回以上の入金の遅れが生じている場合 ● 急に大きな取引を依頼してきた場合 ● 他社との取引について取引停止や、支払い遅れの情報をキャッチした場合 ● 1回目の不渡り情報を入手した場合 |
保証人や抵当権の設定ができない場合の対策
相手との関係や協力が得られないなどの理由により、保証人や抵当権の設定ができない場合には、次のような方法で債権を保全することが可能です。
反対取引による相殺決済
「相殺」とは、自分と相手がお互いに債権を有している場合に、同額の部分についてこれを帳消しにする手続きをいいます。
民法 第505条
第1項
二人が互いに同種の目的を有する債務を負担する場合において、双方の債務が弁済期にあるときは、各債務者は、その対当額について相殺によってその債務を免れることができる。ただし、債務の性質がこれを許さないときは、この限りでない。
相殺手続きは、相手方への一方的な意思表示によりこれを行うことができます。
しかし通常は、意思表示の有無をはっきりさせるために、配達証明と内容証明により相手方へ通知するのが一般的です。
なお、相殺手続きは、双方の債権が弁済期を迎えている必要があります。
そのためどちらか一方の債権が弁済期前の場合には、これを行うことができません。
また、債権の一方が「不法行為による損害賠償債権」または「 差押禁止債権又は 差し押さえられた債権」の場合にも相殺をすることはできません。
相殺の具体例としては、次のようなケースがあります。
・A社がB社に対して500万円の売掛金を有している。(支払期限到来済)
・B社はA社に対して400万円の売掛金を有している。(支払期限到来済)
・A社はB社に対して、相殺の意思表示をする。
・A社はB社に対して、100万円(500-400万円)のみを支払う。
したがって、これをうまく利用すれば次のようなことができます。
A社はB社に対し300万円の商品を販売し、300万円分の売掛金を持っているが、その支払いに不安があるような場合、A社はB社から同額の商品を仕入れること(これにより B 社から A 社に対する300万円の売掛金が発生)で、相殺状態を作り出すことができます。
ただしこの場合には、次のことに注意する必要があります。
① 請求の種類は同じ売掛金として、他の種類の請求としない
② 支払い期日は自社の売掛金の期日と同じ日付にしておく
①については、相殺をする場合は同種の債権でなければならないという規定があるためです。貸金などの請求権は別のものとなりますので、同じ売掛金にそろえるようにする必要があります。
②については、 双方の債権は相殺適状となっている必要があるため、できるだけそれぞれの債権の支払期限を同じにする必要があります。
このように、あえて相殺状態を作り出すことにより、万が一の支払い不能の場合には、相殺により実質的な回収をすることが可能となります。
自社への手形の振り出し
相手が手形の振出をすることができる会社である場合には、 自社宛に手形を振り出してもらうことによっても、代金の保全をすることができます。
なお、この場合には、あらかじめ相手会社の代表者に裏書をしてもらっておけば、会社と代表者個人の両方に対して手形の支払いを請求することができます。
ただし、その際に注意しなければならないのが、「安易に振り出された手形を支払いに回したり、割引をしない」ということです。
なぜなら、もし、自分の支払いにあてるために手形を譲渡したり、銀行で割引きをすると、その後にその振り出し会社が不渡りを出してしまった場合には、その会社だけでなく自分にも支払い責任が生ずるからです。
なので、振り出された手形については、 支払い期日を待って請求するというのが安全といえます。
敷金・保証金への質権設定
以上の方法が使えない場合に検討したい保全方法が「敷金・保証金への質権設定」です。
債務者が入居している住居又は事務所について敷金や保証金がある場合は、これに対して質権の設定をすることができます 。
この保証金への質権設定は抵当権の場合と違って、登記の必要がなく、当事者間の約定だけでこれを行うことができます。
ただし判例によれば、質権を有効に成立させるためには、相手方から建物賃貸借契約書などの保証金等の差入書の原本の交付を受ける必要があるとされています。
また、質権が設定されたことを大家に対抗するためには、 内容証明などの確定日付のある証書により通知をする必要があります。
なお、敷金や保証金へ質権設定をする場合には、敷金や保証金は、あくまでも大家が「退去時の原状回復費用の補填にあてるための預り金」だということに注意してください。
そのため、 保証金等のすべてが原状回復費用で使われてしまった場合には、その質権にもとづく回収ができなくなることになります。
まとめ
新規の企業や、取引の浅い企業と大きな取引をする場合には、あらかじめ相手の意図や素性、財務内容などに関する情報を掴んでおく必要があります。また、それとともに、トラブルや相手方の支払い不能などがあった場合への対応についても準備しておく必要があります。
代金の保全方法には、保証人の徴求や抵当権・質権の設定、相殺など、いろいろな方法がありますが、最も効果的な対策は「相手の信用力を見抜く」ことと「危険な相手とは取引しない」という決断です。
これらについては、事前に社内で与信についてのルールを定めておくことで対応することができます。
119番資金調達NETでは、取引の際の調査や社内ルールの作成、対策に関するアドバイスを行っています。
随時、初回の相談無料でご利用いただけますので、お気軽にご相談ください。
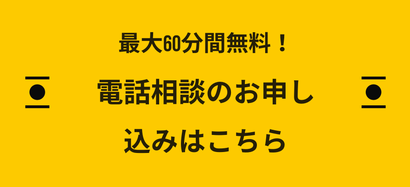
※ こちらから電話できます。