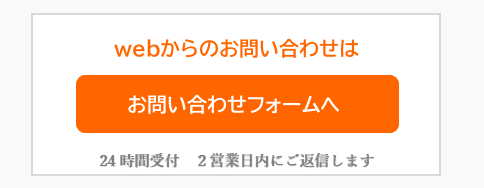融資を利用する際に重い負担となるのが、経営者の連帯保証です。
日本政策金融公庫では「新規開業・スタートアップ支援資金」や「経営者保証免除特例制度」などにより、経営者の保証なしで融資を受けられる取組みが実施されていますが、これまで信用保証協会付融資については、経営者の保証は不可欠のものとなっていました。
しかし、信用保証協会でもこれらの制度を緩和し、東京都制度融資では「創業経営者保証不要型」により、経営者の保証なしで信用保証協会付融資を利用できるようになっています。
この記事では「創業経営者保証不要型」の利用条件や金利、利用可能額について解説いたします。
「創業経営者保証不要型」融資とは?
「創業経営者保証不要型」は令和5年3月15日に、「スタートアップ創出促進保証制度」に準拠した経営者保証を不要とする融資制度として創設された、東京都が行う制度融資の一つです。
なお、制度融資とは、都道府県や市区町村などの自治体が制度を作り、金融機関が融資をし、信用保証協会が公的な保証をするという役割にもとづいて行う、いわば保証付きのパッケージ型融資をいいます。
この融資では、経営者の保証が要らないだけでなく、東京都からの2/3の保証料補助が受けられる等のメリットがあります。
「創業経営者保証不要型」の概要
利用できる方
「創業経営者保証不要型」を利用できるのは、「創業を予定されている方」または「創業後5年未満の法人」のいずれかとなります。
〈創業を予定されている方〉
以下のいずれかに該当する方
●事業を営んでいない個人で、2か月以内※に法人を設立して事業を開始する具体的な計画がある方 ※一定の要件に該当するときは6か月以内
●分社化により別法人を設立して事業を開始する予定の法人
〈創業後5年未満の法人〉
以下のいずれかに該当する方
●事業を営んでいない個人が設立した法人で、設立から5年未満である
●分社化により別法人として新たに設立した法人で、設立から5年未満である
●事業を営んでいない個人が開始した事業を法人化し、個人創業時から5年未満である
※保証申込受付時点において税務申告1期未終了の創業者の方は、創業資金総額の1/10以上の自己資金を有している必要があります。
保証限度額
3,500万円 責任共有制度の対象外(100%保証)
対象となる資金
運転資金および設備資金
申込方法
金融機関経由で申込み
返済期間
10年以内(据置期間 1年以内又は3年以内を含む)
保証期間
10年以内(据置期間1年または3年以内)
担 保・保証人
不 要
利 率
【固定金利】 3年以内 1.5%以内 3年超5年以内 1.6%以内 5年超7年以内 1.8%以内 7年超 2.0%以内
【変動金利】「短プラ+0.2%」以内
保証利率
0.35~0.60%(創業関連保証の保証料率に0.2%上乗せ)から、東京都が2/3を補助。
提出書類
通常の制度融資の必要書類の他に、創業計画書(「スタートアップ創出促進保証制度」用)の提出が必要となります。
現行メニュー「創業」との比較
現行メニュー「創業」の概要
現在、東京都制度融資には、創業者を対象とした融資メニュー「創業」がありますが、これについては「創業経営者保証不要型」の実施後も並行して継続されます。 ※東京都制度融資「創業」
現行メニュー「創業」の概要は、以下の通りとなります。
利用できる方
次のいずれかに該当する方
●現在、事業を営んでいない方で、1か月以内に新たに個人で、または2か月以内に新たに会社を設立して東京都内で創業しようとする具体的計画をお持ちの方
●創業した日から5年未満の中小企業者、組合
●創業又は都内での分社化から5年未満の中小企業者 など
融資限度額
3,500万円
返済期間
運転7年・設備10年(いずれも据置1年以内)
利 率
1.5%以内~2.5%以内(責任共有制度の対象外となる場合)
信用保証料
東京都が3分の2を補助
保証人
必要となることがある
担 保
不 要
東京都「創業経営者保証不要型」と「創業」の違いとポイント
東京都「創業経営者保証不要型」と「創業」は、いずれも創業者を対象とした融資制度ですが、以下のような違いがあります。
法人を設立することが前提
創業者が「創業経営者保証不要型」を利用するには「事業を営んでいない個人で、2か月以内に法人を設立し事業を開始する具体的な計画があること」が要件となります。
そのため、法人を設立する予定がない方や個人で事業を行う予定の方は利用できません。
これに対して、「創業」の場合には、法人だけでなく個人事業でも利用することができます。
保証限度額や資金使途などは同じ
「創業経営者保証不要型」の保証限度は3,500万円、資金使途は設備・運転資金、 申込方法は金融機関経由と、これらの点については「創業」と違いはありません。
ただし、「創業経営者保証不要型」では、保証額のすべてが責任共有制度の対象外(100%保証)となります。(「創業」では、対象・対象外を選択可)
「責任共有制度」とは、信用保証協会が保証をした事業者が返済不能となった場合、金融機関がそのうちの20%を負担する制度をいいますが、本制度ではその対象外となるため、事業者に倒産などの事態が生じても信用保証協会が100%を保証します。
これにより、金融機関では責任共有制度の対象となっている制度よりも安心して利用できるため、結果的に申込者にとっても使いやすくなるという特長があります。
融資利率と保証料
「創業経営者保証不要型」と「創業」のいずれも、融資利率は1.5~2.0%以内(3年~7年)です。
しかし、保証料については「創業経営者保証不要型」では0.35~0.60%であるのに対し、「創業」では信用保証協会が定める保証率となっています。
なお、いずれの制度についても、保証料の2/3を東京都が補助します。
創業計画書の作成が必要
「創業経営者保証不要型」と「創業」のいずれも、融資申込の際には「創業計画書」の作成が必須となります。
創業計画書の融資の様式や記載内容は、制度融資を主宰する都道府県により多少、異なりますが、だいたいの項目は共通したものとなっています。 ※東京都制度融資「創業」の計画書例
開業後1年未満の場合には、自己資金が必要
「創業経営者保証不要型」制度を利用する場合には、保証申込受付時点で税務申告1期未満の創業者の方は、創業資金総額の1/10以上の自己資金を有している必要があります。
そのため、自己資金がない場合にはエントリーができないだけでなく、自己資金がある場合でもその額がわずかである場合には、まとまった融資を利用できなくなってしまうことに注意してください。
一方「創業」では、具体的に自己資金が必要とは定められていません。
ガバナンス体制の確認が必要
「創業経営者保証不要型」制度を利用した場合は、原則として、法人設立から3年目と5年目に、ガバナンス体制の整備に関するチェックを受け、「ガバナンス体制の整備に関するチェックシート」を金融機関に提出する必要があります。
一方、「創業」では、このような条件はありません。
まとめ
東京都制度融資の「創業経営者保証不要型」は、経営者の保証が不要となる融資であり、これを利用することで企業経営者が連帯保証をせずに借入れをすることができます。
また、既存の制度である東京都制度融資の「創業」と比較した場合、大きな違いは「経営者保証の有無」と「個人事業者の利用の可否」、「融資後のガバナンス体制の確認の有無」の3点となります。
なお、東京都以外の一部の都道府県でも、同様の制度を行っているため、他県の方は自分の県で利用が可能なのかをご確認ください。
119番資金調達NETでは、新規開業資金の申込みのサポートの他、、このブログではご紹介していないテクニックや注意点についても、直接、その方の状況にあわせてアドバイスしています。
随時、初回の相談無料でご利用いただけますので、お気軽にご相談ください。
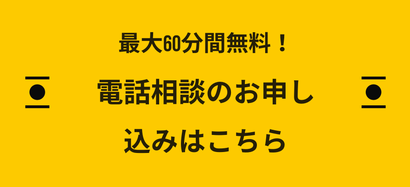
※ こちらから電話できます。