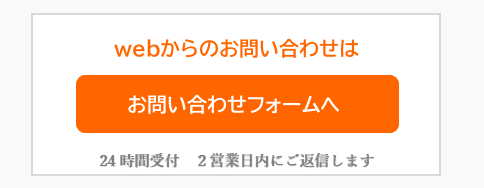開業予定の方からの質問で一番多いものに
「自分の場合は、いくらまで融資を借りられますか?」
というのがあります。
新規の開業には多額の資金が必要となるので、できるだけ目いっぱい借りたいという気持ちはわかりますが、自分の実力を超えて融資を申し込んでも満足のいく結果にはなりません。
とはいえ、少なすぎて、必要な資金が足りなくなってしまうのも困ります。
そのため、「最も借りられる可能性のある額」を申し込めれば一番よいのですが、なかなかその見極めは難しいのではないかと思います。
そこで、ここではすぐにできる「最適な融資の申込額を簡単に算定する方法」をお伝えします。
「融資上限額」と「借入限度枠」との違い
融資の申し込みをする際に気をつければならないが、「融資上限額」と「借入限度枠」の違いを理解しておくことです。これを間違えてしまうと、本来の実力では借り入れができない額の申し込みをしてしまうことになるため注意が必要です。
「融資上限額」とは?
融資はそれぞれの制度により、利用できる上限額が決まってきます。
例えば、創業者が利用できる代表的ないくつかの融資を比べた場合、次のようになっています。
| 取扱金融機関 | 融資の種類 | 融資上限額 |
| 日本政策金融公庫 | 新規開業・スタートアップ支援資金 | 7,200万円 |
| マル経融資 | 2,000万円 | |
| セーフティネット貸付 | 4,800万円 | |
| 東京都制度融資 | 創業経営者保証不要型 | 3,500万円 |
このように、融資の制度で定められている最大限利用可能な限度額のことを「融資上限額」といいます。
そのため、だれもがこの限度額で申し込めるわけではありません。
「借入限度額」とは?
では、融資上限額ではないとしても、もし、創業者がいきなり「新規開業・スタートアップ支援資金」に3,000万円の申し込みをした場合、全額を借りられるでしょうか?
「答えは「NO」です。
通常は、3,000万円の申込みをしたとしても、実際には最大でも「1,000万円~1,500万円」程度の融資しかされないのが普通です。
なぜこういうことになるかといえば・・・
それは、一般的な創業者の方では、3,000万円を貸すだけの信用力がないと判断されるからです。
このように制度としての「融資上限額」とは別に、
現状で、その人の実力で借りられる最大の金額を「借入れ限度枠(もしくは「与信枠」)」
といいます。
つまり、自分がいくらまで借りられるのかを知るためには、「融資上限額」ではなく、その企業の実力にもとづいた「借入れ限度枠」がいくらなのかを知る必要があるわけです。
3,000万円の融資を申し込んだ場合
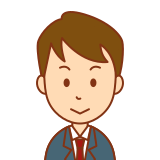
A社 2,500万円を獲得!

B社 1,500万円しか借りられない・・・
「無担保・無保証枠」とは?
なお、これと似たものに制度融資の「無担保・無保証枠」というものがあります。
「制度融資」とは、行政(都道府県・市区町村)と金融機関、それと信用保証協会が協調して、中小企業に対する融資をする仕組みをいいます。
制度融資における役割
● 行政(都道府県や市町村) ➡ 制度融資の仕組み作り、運用をします。
● 金融機関 ➡ 窓口となって融資の資金を提供します。
● 信用保証協会 ➡ 公的な保証人となります。
この「制度融資」では、すべての人に最大8,000万円の無担保・無保証で利用できる保証枠が与えられています。
つまり、信用保証協会を利用して無担保無保証で融資を借りる場合、借入限度額の最大額はこの無担保・無保証の限度額ということになります。
でも、これについても、先のケースと同じで、誰もが8,000万円の無担保・無保証枠を使えるわけではありません。
しかし、中にはこれを誤解して
「自分には8,000万円の枠があるから、あと2,000万円を無担保・無保証で借りられるはずだ!」
などという方がいます。
けれど、これはそういうことではなく、信用保証協会や金融機関が
「現時点で、ここの会社に与えられる保証枠は6,000万円まで」
と判断すれば、それ以上の枠を利用することはできないわけです。
このように、いくらまで無担保・無保証枠が使えるかは、その企業の実力次第となりますが、具体的な額は金融機関が判断することとなります。
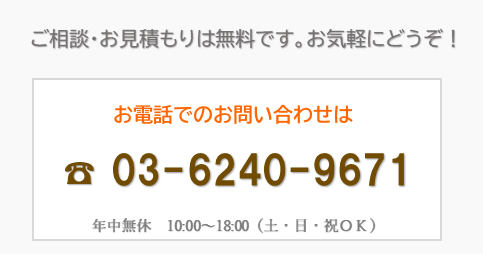
※ ここから電話できます。
なお、無担保・保証枠は、特定の企業ごとに与えられる保証の総枠であることから、利用した保証付融資額が大きくなるほど、その後に使用できる保証額は少なくなっていきます。
そのため、制度融資を利用する場合には、ある融資の融資限度枠が8,000万円あっても、その企業に与えられる保証枠が5,000万円であり、その後に4,000万円を使用した場合には、残り1,000万円の保証枠しか利用できないということになります。
例) A社が使える無担保・無保証の残額
| 無担保・無保証の最大保証枠 | 8,000万円 |
| A社に与えられた無担保・無保証の枠 | 5,000万円 |
| A社が無担保・無保証で融資を受けている額 | 4,000 万円 |
| A社が使える残りの無担保・無保証枠の額 | 1,000万円 ※8,000万円-5,000万円ではない |
「借入限度枠」を知る方法

では、具体的な「借入限度枠」を知ることはできないのでしようか?
借入限度枠は、金融機関や信用保証協会がそれぞれの企業に設定するものなので、これを正確に知ることは難しいですが、およそであれば、次の方法により知ることができます。
金融機関に確認する
具体的な「借入限度枠」を知る上で一番手っ取り早いのは、「直接、金融機関に聞いてしまう」という方法です。
そのお客のデータや過去の履歴など、取引先の金融機関では「その人に、あといくらまでなら貸せるか?」といった限度をかなり正確に把握しています。
しかし、すべての金融機関がこれを教えてくれるわけではなく、また、親しい取引先だけにしか教えないというところもあります。
なので、すべてのケースで使える方法ではありませんが、もし、使えるのなら最も手っ取り早い方法ですので、一度、チャレンジしてみてください。
算定式を使って計算する。

金融機関に聞くことができなくとも、ある程度であれば次の算定方法を使って、借入限度枠を試算することができます。
➀ 現状で借り入れできる最大限の金額を計算してみる。
現状で借り入れができる最大限の金額は、「税引後利益+減価償却費」に借りたい年数をかければ求めることができます。
もし、会社の「税引後利益+減価償却費」が300万円/年で、返済期間を5年と考えているならば、計算上の借り入れ可能額は300万円/年 × 5年 = 1,500万円となります。
| 現状で借りられる最大額 ( 税引後利益+減価償却費 ) × 返済期間の年数 - A |
※ 減価償却に必要な耐用年数は国税庁耐用年数一覧表で確認できます。
➁ 融資の残債がある場合にはこれを差し引く
もし、その会社に以前の融資の残債がある場合には、上のAから残債額を差し引きます。
この会社の残債額が600万円の場合は、1,500万円 – 600万円 = 900万円が計算上で借りられる額となります。
他の融資の残債がある場合の借りられる最大額
A - 他の融資の残債額
これを表にすると、次の通りとなります。
| 実質的な返済力/年 | 300万円(250+50万円) |
| 予定返済期間 | 5年 |
| 想定借入限度額 | 1,500万円(300万円×5年) |
| 融資残債額 | ▲600万円 |
| 実質借入限度額 | 900万円(900-600万円) |

何年で返済するかがポイントですね!

それによって、計算上の借入れ最大額が変わります。
したがって、税引後利益や減価償却費の額が少ない場合には、それに応じて借入限度額も少なくなってしまいます。
次は開業予定の居酒屋のケースです。
● 予想される税引後利益 300万円/年
● 予想される減価償却費 30万円/年
● 既存の融資額の残債額 0円
● 融資の返済期間 5年
● 自己資金額 200万円
この場合には先ほどの例と違って、「税引後利益と減価償却費」は事業計画書の予想額となります。また、既存の融資残高はないので、融資の申込額を使って計算します。
このケースでは、「(300万円+30万円)× 5年 = 1,650円」となります。
| 実質的な返済力/年 | 330万円(300+30万円) |
| 予定返済期間 | 5年 |
| 想定借入限度額 | 1,650万円(330万円×5年) |
| 融資残債額 | 0円 |
| 実質借入限度額 | 1,650万円 |

創業の場合には、計画の見込みが基本になるんですね。

但し、根拠のない利益にならないよう気をつけてください。
借入限度額と自己資金の関係

創業融資におけるもう一つの注意点
創業融資のうち、日本政策金融公庫の「新規開業・スタートアップ支援資金」については、それまで求められていた自己資金の条件がなくなったため、これを考慮する必要がなくなりました。
しかし、東京都制度融資「創業経営者保証不要型(略称:創業経保)」※のように、一部の融資については相変わらず自己資金の保有が必要となるものもあります。 ※創業にかかる経費の1/10以上の自己資金が必要
その際に注意しなければならないのが
「 借入れ額と自己資金額のバランス 」
です。
創業融資では、仮に制度上の限度額が3,000万円となっていても、実際に借りられるのは「自己資金額の3~4倍程度」というのが一般的です。
仮に、自己資金額が200万円しかない場合、計算上の借りられる最大額が1,650万円だとしても、自己資金の額から考えた妥当な額としては600~800万円程度(200万円の3~4倍)となります。
このように創業融資の場合には、冒頭の算定式がそのまま当てはまらないこともあることに注意してください。
参 照 最新の実例見本で解説! 飲食店創業融資のための事業計画書(創業計画書)の作成
借入れ可能性の高い融資の額の求め方
以上のことをまとめると、次のような感じになります。
| 基本的な考え方 ● お店等の運転資金の「3~4ヶ月分」+設備費が一般的な融資申込額の目安 ● 運転資金が150万円/月、設備費300万円ならば (150万円×3~4ヶ月分)+300万円 = 750~900万円 ● 各企業には個別に借入限度枠が決められているので、申込みはその範囲内 借入限度枠は「金融機関に確認」または「自分で計算」で求める ● 創業融資の場合には、自己資金とのバランスにも注意。 |
| 返済原資からの考え方 ● 返済の原資となるのは、「減価償却費+税引き後利益」の合計額 なので、借りられる金額の目安は、 (「減価償却費+税引き後利益」 ✖ 返済期間 ) - 既存の借入額 |
| 事業計画書の必要性 ● 事業計画は、返済原資額以上の利益が出せる内容のものが必要 ● しかし、利益がこれを下回る見込みならば融資は困難。 なので、事業計画にはどうやってその不足分を補うかを示す必要あり |
| 対策のポイント 融資の申込み額は「融資額がいくら欲しいからから」ではなく、 ◎「事業に必要な金額」についての正確な見積もり ◎「〇〇だから、いくらまでなら返済できる」という根拠 がワンセットとなって、はじめて現実的なものとなる。 なので、過大な額の申し込みや売上げや利益の根拠のない申込みをすると、融資否決や秘訣や融資額の減額をされる可能性が大きくなってしまう。 |
まとめ
融資には、制度上の上限額出る「融資上限額」と「借入限度額」がありますが、できるだけ多くの金額を借りるためには、自らの借入限度額を把握しておく必要があります。
借入限度額は「( 税引後利益+減価償却費 ) × 返済期間の年数」で求めることができますが、税引後利益や減価償却費の額が少ない場合には、それに応じて借入限度額も少なくなってしまいます。
また、創業融資で自己資金の保有が条件となっている場合には、自己資金額と申込額とのバランスに注意する必要があります。
なお、119番資金調達NETでは、新規開業資金の申込みのサポートの他、、このブログではご紹介していないテクニックや注意点についても、直接、その方の状況にあわせてアドバイスしています。
随時、初回の相談無料でご利用いただけますので、お気軽にご相談ください。
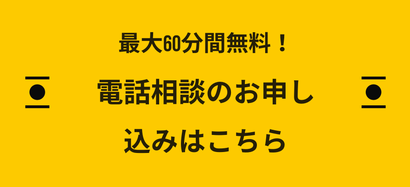
※ こちらから電話できます。