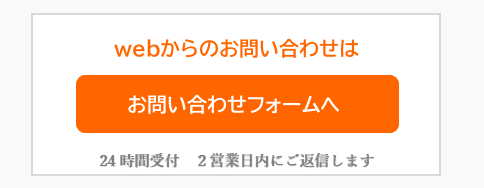これまで多くの創業者の方に利用されてきた日本政策金融公庫の新創業融資がなくなり、「新規開業・スタートアップ支援資金」としてリニューアルしました。
「新規開業・スタートアップ支援資金」には、これまで必要とされてきた1/10以上の自己資金の必要がなくなる、金利優遇制度と併用できるなど、以前の新創業融資にない特徴があります。
しかし、この制度については勘違いされていることも多く、その点をよく理解しないで申し込むと大きな損をしてしまう可能性があります。
この記事では、日本政策金融公庫の担当者から直接ヒアリングした内容もご紹介しながら、「新規開業・スタートアップ支援資金」の役立つメリットや、実際にこの制度で融資を申し込む際の注意点について解説いたします。
「新規開業・スタートアップ支援資金」について
この章では「新規開業・スタートアップ支援資金」に関する注意点の前に、まずはどのようにしてこの融資ができたのかや、その特徴について解説いたします。
「新規開業・スタートアップ支援資金」の成立の背景
これまで日本政策金融公庫では、長年にわたり創業者向けの融資として、「新創業融資制度」を実施してきました。
この新創業融資の主な特徴をまとめると、次のようものとなっていました。
【以前の新創業融資制度の特徴】
・新たに事業を始める方または業開始後税務申告を2期終えていない方が利用できる
・無担保無保証で利用できる
・利用するためには創業にかかる経費の1/10の自己資金が必要
しかし、この制度の中身は融資の無担保無保証での利用を可能とするため、既存の制度(以前の新規開業資金など)をベースとし、それに新創業融資制度という無担保無保証のための枠を重ねて使うという、かなり変則的な運用となっており、これを整理する必要がありました。
また、最近になって、政府が創業者の割合を他の先進国並みにするという目標を掲げ、その資金調達先の主力となる日本政策金融公庫の融資を原則、無担保無保証とする政策を実施したことも相まって、2024年3月末に新創業融資制度は廃止となりました。
「新規開業・スタートアップ支援資金」の3つの大きなポイント
そして2024年4月から新たに開始されたのが「新規開業・スタートアップ支援資金」です。「新規開業・スタートアップ支援資金」には、3つの大きな特徴があり、これを新創業融資制度と比較すると以下の通りとなります。
【「新規開業・スタートアップ支援資金のポイント】
● 無担保・無保証人融資で融資が利用できる
● 融資の利率が一律0.65%引下げられる
● 長期での返済が可能
● 自己資金不要で申し込める
また、以前の新創業融資と比較すると、次のような違いがあります。
| 新規開業・スタートアップ | 新創業融資 | |
| 融資限度額 | 7,200万円(運転資金4,800万円) | 3,000万円(運転資金1,500万円) |
| 返済期間 | 設備資金 20年以内 運転資金10年以内 | 各融資制度に定める返済期間以内 |
| 利率 | 基準金利 ※創業者は0,65%引下げ | 基準金利 |
| 担保・保証 | 不要 | 不要 |
| 自己資金 | 不要 | 創業にかかる経費の1/10以上必要 |
1. 無担保・無保証人融資で融資が利用できる
「新規開業・スタートアップ支援融資」を利用できる方は、無担保無保証で融資を利用できます。
2. 融資の利率が一律0.65%引下げられる
新たに事業を始める方または事業開始後税務申告を2期終えていない方は、原則として、金利が0.65%引下げとなります。
また、雇用の拡大を図る事業を行う場合は、0.9%の引き下げとなります。
2025年4月現在の税務申告を2期終えていない方向けの基準金利は、3.00~4.10%/年となるため、上記要件を満たす方はこれから0.65%または0.9%の引き下げとなります。
3. 長期で返済での返済が可能
「新規開業・スタートアップ支援融資」の返済期間は、最大、設備資金 20年以内、運転資金 10年以内と長期で設定されています。
また、設備資金・運転資金のいずれについても、5年以内の据置期間が利用できます。
※据置期間…利息の返済だけで元本の支払いが不要な期間
4.自己資金不要で申し込める
「新規開業・スタートアップ支援融資」は、新創業融資制度とは異なり、自己資金がなくとも申し込める制度です。
しかし、これはあくまでも「申し込みができる」ということであり、実際に十分な融資を受けるためには、ある程度の自己資金が必要となります。
※この点については後述します。
「新規開業・スタートアップ支援融資」で勘違いしやすいこととは
「新規開業・スタートアップ支援融資」の主なポイントは前述したとおりとなりますが、勘違いしやすい点も多いため、利用の前には以下の点に注意する必要があります。
実は、2期過ぎても無担保無保証で申し込める
「新規開業・スタートアップ支援融資」は、以前の新創業融資とは異なり、自己資金がなくとも申し込むことができます。
これについて、日本政策金融公庫のHPの創業期向けの案内では、
「新たに事業を始める方または事業開始後税務申告を2期終えていない方は、原則として無担保・無保証人で各種融資制度をご利用いただけます。」
となっています。 参考:創業融資のご案内より
これを普通に読めば、「新たに事業を始める方または事業開始後税務申告を2期終えていない方」だけが、無担保・無保証人で融資制度を利用できるように受け取れます。
しかし、公庫の担当者によれば、これはそういうことではなく
「新規開業・スタートアップ支援融資」を利用できる方であれば、期間に関係なく、無担保無保証で利用できる
とのことです。
つまり、この制度は最大で事業開始後おおむね7年以内の方ができるため、最大で7年の間、無担保無保証で利用できることとなります。
なお、7年を過ぎたときには無担保無保証融資が利用できなくなるわけではなく、「経営者保証不要制度」を利用することで無担保無保証で利用することができます。
自己資金は不要だが、自己資金の審査は行われる
「新規開業・スタートアップ支援融資」は、自己資金不要で利用することができますが、自己資金の審査が行われないわけではありません。
なぜなら、融資では相変わらず自己資金はある方が有利となるため、その確認のための審査が必要だからです。
この点について公庫の担当者は
「制度としての自己資金要件はなくなったが、自己資金がある方が有利になるのはこれまでと同じであって、その判断をするためにも、自己資金の有無は確認する」
と明言しています。
中には、「新制度では自己資金の要件がなくなったのだから、その点に関する審査もなくなったろう」と考える方も多いと思いますが、自己資金の保有の有無に限らず、確認や審査は行われるとのことです。
自己資金がないと、融資はかなり難しくる可能性が高い
自己資金がない場合の取り扱いについても確認したところ、
「自己資金は
・これまでに資金をためてきた努力や経緯
・これがない場合、結果的に融資額が大きくなる分だけ返済が困難になる
という2点において、融資審査でもその有無は重要なポイントなる。
したがって、自己資金がまったくない申し込みは、かなり難しいものになる可能性が高い」
との回答でした。
つまり、これをまとめると、自己資金がなくとも申し込みはできるものの、融資を成功させるためには、ある程度の自己資金は相変わらずあった方がよいということになります。
「自己資金が不要になった」=「なくても融資が出やすくなった」というではないことに注意が必要です。
なお、余談として、「親兄弟から支援資金として贈与された資金は自己資金となるか?」についても確認しました。
この点については「親からの贈与はその贈与のエビデンス(通帳の振り込み記録等)で贈与が明らかな場合には、原則、自己資金として認められる。」とのことでしたので、この点ついては従来と変更はないようです。
法人代表者は連帯保証人にならない
「新規開業・スタートアップ支援融資」では、新たに事業を始める方や事業開始後税務申告を2期終えていない方が、無担保・無保証人で融資を利用できる制度となっています。
以前の新創業融資制度では、代表者は連帯保証人とならないことができるとハッキリ明示されていましたが、「新規開業・スタートアップ支援融資」ではこの点が明確となっていません。
この点について確認したところ、「法人が申し込んだ場合、その代表者は連帯保証人ならない」という回答がありました。
そのため、これからこの融資制度で申し込みをする場合には、個人よりも法人で申し込む方がリスクが少なくて済むといえます。
制度融資との併用は、内容が重複しなければ問題ない
通常、創業者の方が利用できる融資には、日本政策金融公庫の融資とは別に信用保証協会の保証のついた制度融資があります。
日本政策金融公庫と信用保証協会は別の組織、運営であるため、審査の内容は共用されず、そのためこれらを同時に申し込むことも可能です。
しかし、この点について明確にされた資料などはないため、これについてもあらためて確認しました。
この点についての公庫の担当者の回答は
「融資の申し込みの内容で重複するものがなければ、基本的には問題ない。」
とのことでした。
つまり、同じ設備の購入を両方に申し込みをせず、設備については日本政策金融公庫へ、運転資金については制度融資へなどのように、シッカリと内容を分ければよいということになります。
この点については、当サイトでも以前からご案内してきた「日本政策金融公庫と信用保証協会融資を同時に獲得する方法」の記事のとおりとなるため、キチンとした方法であれば、日本政策金融公庫と制度融資の同時申し込みにより、一度で得られる融資額を増やすことができます。
その他
公庫の正式な回答ではありませんが、新創業融資を扱ってきた中で得られた情報や当サイトの考えを以下にまとめたので、よろければご参照ください。
自己資金の何倍までなら融資が出やすいか?
日本政策金融公庫の担当者の回答によれば、「新規開業・スタートアップ支援融資」でもある程度の自己資金はあった方がよいということでしたが、それでは「自己資金額の何倍くらいの融資が出る」のでしょうか?
残念ながら、この点についての明確な回答はありませんでした。
しかし、以前の新創業融資制度では、制度上は自己資金の最大9倍(1-1/10)まで可能とされていたものの、実際に利用できる融資の額は自己資金額の3倍程度となっていました。
そこのことから、今回の「新規開業・スタートアップ支援融資」でも、自己資金の3倍程度までが融資の出やすいレベルではないかと考えられます。
つまり、自己資金が300万円ならば、1,000万円程度までが実質的な限界ということなります。
自己資金がない場合は、いくらくらいまで利用が可能か?
「新規開業・スタートアップ支援融資」は、制度上は自己資金不要となっていますが、実際の申し込みにおいて自己資金がまったくないのは、かなり難しいという公庫担当者の回答をご説明しました。
では、自己資金がまったくない場合には融資は受けられないのかといえば、そんなことはないと思います。
しかし、自己資金がない場合に利用できる融資の額は300万円程度ではないかと思われます。
その理由としては
・300万円くらいまでならば審査のハードルが低くなりやすいこと
・300万円を5年(60回)で返済する場合、1回あたりの返済額は5万円、7年(84回)で返済する場合は約3.6万円となることから、無理なく返済しやすい額であること
などが考えられます。 ※とりあえず、ここでは利息は考えないものとします。
しかし、事業計画の内容がずさんだったり、これだけの利益が見込めないと判断されるようなケースでは、300万円でも融資が出ない可能性が高くなります。
まとめ
「新規開業・スタートアップ支援融資」 は、以前の新創業融資制度に代わり、創業者の方が無担保無保証で利用できる融資です。
また、それ以外にも金利の引き下げやさらに大きな融資額に対応しているなど、さらに使いやすいものとなっています。
しかし、「いつまで無担保無保証が使えるのか?」や「法人代表者の連帯保証はどうなるのか?」などについては、通常の融資とは異なる部分もあるため、これらの点について理解して利用する必要があります。
119番資金調達NETでは、事業計画書の作成や資金調達全般に関するサポートの他、このブログではご紹介していないテクニックや融資で注意すべき点についても、その方の状況にあわせてアドバイスしています。
随時、初回は相談無料でご利用いただけますので、お気軽にご相談ください。
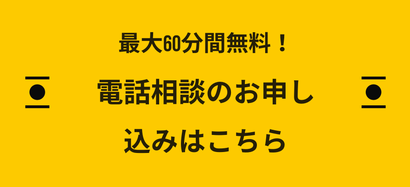
※ こちらから電話できます。