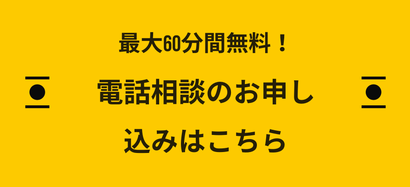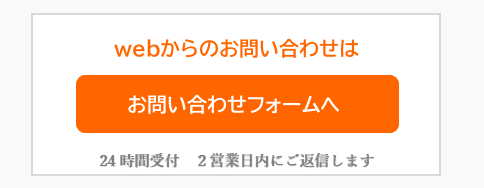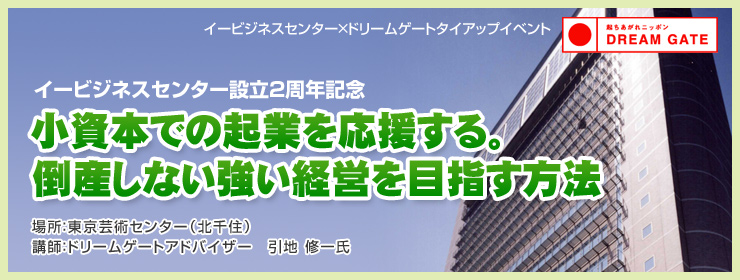信用保証協会付融資を利用された方の中には、その後の返済が滞り、代位弁済をされているという方もいらっしゃると思います。
代位弁済がされると、債務を完済するまで高率の遅延損害金を支払わなければならなくなったり、新規の保証や融資が使えなくなるなど、厳しいペナルティがあります。
しかし、ずっと完済までこの状況が続くのかというと、必ずしもそうではなく、その救済方策の一つとして、信用保証協会の求償権消滅制度が設けられています。
この記事では、この「求償権消滅保証の概要と要件」、「制度を利用した事例」について解説します。
求償権の消滅保証制度の概要
求償権の消滅保証制度の仕組み
たとえば、ある企業が信用保証協会の保証付き融資(「制度融資」を含む)を利用し、その返済ができなくなった場合、信用保証協会は金融機関に対してその残債を肩代わりして支払います。
そして、それ以降は信用保証協会が金融機関に代わって、債務者に返済を請求することとなります。
これにより、信用保証協会はそれまで金融機関が債務者に対して有していた請求をする権利を取得し、以降、信用保証協会がその企業に支払いを請求することができるようになります。この権利のことを「求償権」といいます。
いわば、信用保証協会が債務の支払いを肩代わりしたことで、自分がその肩代わりした分を取り立てることができるようになるわけです。
これまでも求償権については、債務者の状況によりこれを消滅させるという手続きを行ってきましたが、あくまでも信用保証協会の好意で行うという側面が強いものでした。
しかし、中小企業庁は令和5年9月に金融庁・財務省とともに「挑戦する中小企業応援パッケージ」を公表し、その一環として「求償権消滅保証」制度を新設し、これまで相対的な取引の中で行われていた求償権の消滅の手続きを制度化しました。
これにより、この制度の要件に該当する方については、求償権を消滅させるための保証を利用し、債務の正常化をする道筋が整ったことになります。
「求償権の消滅保証」制度とは、信用保証協会が新たに同額以上の保証付融資を行って、旧債務(求償権)を消滅させる仕組みです。
これにより、債務者は同じだけの債務を負うことになりますが、新たな貸付は通常の貸付と同様の健全な借り入れとなり、金利も遅延損害金ではなく、一般的な貸出し金利となります。
「求償権消滅保証」を利用するための要件
「求償権消滅保証」制度を利用するための要件は、以下の通りとなっています。
対象者
信⽤保証協会に対して求償債務を負う中⼩企業者であって、事業再⽣を図ろうとする方
主な要件
• 信⽤保証協会の当該中⼩企業者に対する債権の全部⼜は⼀部を消滅させることを⽬的とする保証であること。
• 経営サポート会議※による検討に基づき作成⼜は決定された事業再⽣計画、中⼩企業活性化協議会等の⽀援により策定した再建計画等があること。
• 認定経営⾰新等⽀援機関が経営改善計画策定⽀援事業によって策定を⽀援した事業再⽣計画についても計画要件の対象。
保証限度額・保証期間・保証料率・担保、保証人
利用する保証制度所定の額等(信⽤保証協会・⾦融機関と要相談)
保証割合
100%保証
※ 経営サポート会議︓⾦融機関等の関係者により個々の事業者を⽀援する信⽤保証協会等を事務局とした⽀援の枠組みをいいます
これらの条件を見ると、画一的に決まっているのは保証割合位で、その他については信用保証協会や金融機関との協議によるものとなっています。
そのため、この制度を利用するには、主に信用保証協会の協力が必要となるわけですが、「求償権の消滅保証」が制度化されたとはいえ、信用保証協会の承諾を得るには、以下の程度のことができていなければ、利用が難しいのではないかと思われます。
・代位弁済後も、定められた金額を一定期間以上支払っていること
・その他の信用保証協会が出した条件を守れていること
なお、代位弁済について詳しく知りたいという方は、「信用保証協会の代位弁済とは?具体的な対応例と返済計画の作り方」の記事をご参照ください。
「求償権消滅保証」制度を活用した事例
事 例
以下では、「求償権消滅保証」制度を活用して、求償権消滅と新規保証付き融資を獲得した事例をご紹介します。 ※事例は、信用保証協会事例より引用
【業種】
⾦属製品製造業
【⽀援に⾄るまでの経緯】
• リーマンショックに伴う景況悪化により、売上が減少。以後、業況悪化に⻭⽌めがかからず、2013年に代位弁済。
• 代位弁済後、しばらくは厳しい状況が続いていたが、その後業績は徐々に回復し、協会への求償権返済も順調に継続。
• 令和元年に世代交代し、息⼦が代表者に就任したタイミングで。新規設備導⼊の希望があっため、求償権消滅制度を検討した。
【保証協会によ⽀援内容】
• 会社の資⾦ニーズを受け、求償権消滅保証の引受先として地元⾦融機関に打診した。
• 経営改善計画策定に向け、外部専⾨家(中⼩企業診断⼠)を派遣。
• 経営サポート会議を開催し、計画内容を説明し、保証協会と地元⾦融機関で合意が成⽴。
• 計画に基づき、求償権消滅保証を実⾏。設備資⾦にも対応する形で、⾦融正常化を図った。
【⾦融⽀援】
• 保証協会の求償権10,000千円に対し、設備資⾦を含めた15,000千円の求償権消滅保証を実⾏した。
【⽀援実施にあたり⼯夫した点】
• 保証協会内部(保証審査部署・管理回収部署)では、早期段階から連携し、求償権消滅保証の引受先となる地元⾦融機関にも、専⾨家派遣に同席してもらい、事業性や将来性の理解を深めてもらった。
• 会社の担当税理⼠も、専⾨家派遣に同席し、タックスプランや数値計画の妥当性について事前に確認しながら計画を策定した。
事例のポイント
【早期からの信用保証協会の協力体制】
本事例では、該当会社からの要請に信用保証協会が早期から答えているが、これは普段からの当該会社と信用保証協会の担当者との間で、普段から密なコミュニケーションが図られているとともに、決算書などの財務データを正直に公表していたことが大きなポイントであったと考えられます。
【経営刷新のタイミング】
本事例における手続きがスムーズに進んだ理由としては、直接の借入人であった先代代表者の死去に伴い、経営が刷新されたタイミングであったことも挙げられると考えられます。
通常、借入人である代表者が生存している場合、経営責任のの放棄を簡単に認めることができないため、この点がネックとなり、再生手続きが進まないことがあります。
しかし、本事例では、代表者の交代に伴い、その点があまり問題とならなかった可能性があります。
【地元金融機関の協力の取りつけ】
また、見逃すことのできない点として、地元金融機関の協力の取りつけがあります。
通常、金融機関では「社内に協力体制が構築できていない」、「手間と時間がかかる」、「協力するうえでのメリットが少ない」などの理由により、支援に消極的なところが少なくありません。
私の事務所でも、過去にクライアント企業の再生支援をお願いたことがありましたが、やはり上記のような理由でお断りされたという経験があります。
求償権消滅保証は、信用保証協会の承諾がなければできないものではありますが、それ以前に融資元の金融機関の同意と信用保証協会に対する働きかけの両方がないと実現できません。
そのため、信用保証協会だけでなく、まずは金融機関の協力を取りつけられるかということが大きなポイントとなります。
【求償権額を上回る融資保証について】
この事例では、保証協会の求償権10,000千円に対し、設備資⾦を含めた15,000千円の求償権消滅保証を実⾏していますが、求償権消滅保証は求償権額(残存の保証額)に限らず、必要と認められれば、さらにそれに運転資金や設備資金を上乗せした保証を利用することができます。
【認定経営革新等支援機関による事業再生計画等】
最後に今回の求償権消滅保証については、経営サポート会議や中小企業活性化協議会の関与だけでなく、認定経営革新等支援機関による事業再生計画等が認められた点にあります。
経営サポート会議や中小企業活性化協議会は、弁護士をはじめとした高度な資格者を中心としたものであるため、サポート費用が高額になりやすいという問題がありました。
実際、再生の見通しはあるものの、サポート費用が大きすぎて再生ができないというケースもあります。
しかし、認定経営革新等支援機関には、そこまでのコストがかからず利用できるところもあるため、これを積極的に活用すれば、比較的少ないコストで支援を受けることができる可能性があり、また、一定の要件に該当する場合には、支援費用について国の補助金を利用できる場合があります。
まとめ
これまで代位弁済をされた場合には、その後の資金難や重い返済負担により、事業を再生することが難しいことが多かったといえますが、今回の求償権消滅保証という制度を利用することにより、再起を図ることが可能となりました。
とはいえ、その適用を受けるためにはまだ高いハードルがあるため、まずは事業再生の専門家に意見を求めたうえで、準備・行動をすることをおすすめします。
119番資金調達NETでは、代表が事業再生士捕、事業再生アドバイザーという資格にもとづき、専門的な見地から再生計画の作成やその後の運用のサポートをすることができます。
随時、初回の相談無料でご利用いただけますので、お気軽にご相談ください。
※ こちらから電話できます。