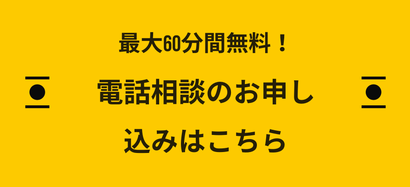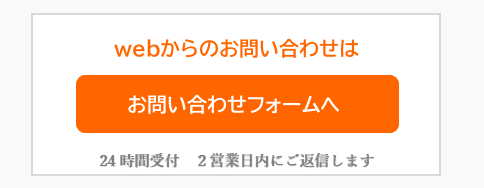これから融資を受けようとされる方の中には、金融機関との面談が怖いという方が少なくと思います。
「どんなことを聞かれるのだろう?」
「うまく計画内容を説明できるだろうか?」
「質問に答えられなかったらどうしよう!」
みなさんが、こんな不安をお持ちになるのはよくわかります。
しかし、金融機関との面談はシッカリ対策をして臨めば、思うほど怖くはありません。
とはいえ、やはりはじめての方にとっては緊張するものですし、言ってはいけないNGなどもあります。
ここでは実際に日本政策金融公庫の面談で聞かれた15の質問を例にして、面談までの流れや、回答のポイントについてご説明します。
- 融資の面談の概要と注意点
- よくある質問と対応例
- ➀ 家賃や公共料金などの支払いが遅れているのはなぜか?
- ② 営業場所はどこなのか?
- ③ なぜ、この事業を始めようと思ったのか?
- ④ これからする事業の経験はどのくらいあるのか?
- ⑤ これまでに何か自分で事業をしたことはあるか?
- ⑥ テナントを借りて営業するのか? なぜその場所で営業するのか?
- ⑦ 営業時間は? 定休日は?
- ⑧ 主力となる商品は何か?
- ⑨ 想定する月の売上げや経費の額はいくらか?
- ⑩ 取引先はどういう会社なのか?
- ⑪ なぜ、計画通りの売り上げを達成できると思うのか?
- ⑫ もし、計画通りにいかず、返済ができなくなったらどうするつもりか?
- ⑬ 営業に必要な許認可の見通しは?
- ⑭ 融資の希望額が大きすぎるのではないか?
- ⑮ 信用保証協会融資(制度融資)への申込みはしているのか?
- 「自己資金」に関する質問は、なくなったのか?
- まとめ
融資の面談の概要と注意点
日本政策金融公庫の面談の流れと概要

日本政策金融公庫での面談は、次のような流れや体制で行われます。
日本政策金融公庫に融資を申し込んだ場合
| ➀「その場で面談日の希望を聞かれる場合」 ➁「何日かして担当者から連絡が来る場合」 |
の2つのケースがあります。
②のケースは、こちらが希望した面談日で調整が取れない場合などでよくあります。
いずれの場合も、金融機関の都合も加味した上で、面談日や場所が決められます。
けれど、必ずそれに従わないといけないわけではありません。
もし、それが自分の都合に合わなければ、ハッキリ自分の希望を伝えましょう。
場 所
面談はあらかじめ指定された日時・場所で行われます。
面談は、通常、日本政策金融公庫や金融機関(制度融資の場合)のカウンターや応接で行われますが、申込人の事務所が面談場所に指定される場合もあります。
申込人の自宅や事務所で面談が行われる場合は、担当者は次のようなことをチェックしているので、あらかじめ必要な対策をしておきましょう。
・事務所等に会社のネームプレートや表札がきちんと掲示されているか?
・事業の作業場所として適切か?(場所や環境など)
・他の会社のスペースの間借りなどではないか?
体 制
面談は、通常、金融機関の担当者1~2名、こちら側1名(本人)という体制で行われます。
しかし、制度融資(信用保証協会付融資)の場合には、さらに信用保証協会の人間がこれに加わることがあります。
なお、面談は公庫の方がいくつかの質問をし、申込人がそれに答えるという形で進められます。
事業計画書などの資料がある場合には、事前に提出するか、この面談の際に持参するかのいずれかとなります。
面談の時間は「約30分~40分程度」というのが一般的です。
しかし、内容に不審な点がある場合や、深く事情を聞きたいような場合には、さらに時間をかけて行われます。
事業の内容に不審な点があるような場合には、1時間を超えて行われることもあるため、できるだけ聞かれそうなことを整理し、不審と思われそうな項目については事前に対策しておきましょう。
質問の内容
面談での質問の内容は、新たに行う事業に関する基本的な項目がほとんどです。
なので、事業の中身がシッカリと頭に入っていれば、特に問題ありません。
とはいえ、ときにはすぐに答えにくいものや、意地悪な質問がされることもあるため、しっかりと準備しておく必要があります。
よくある質問と対応例

面談ではいろいろな質問がされますが、その中でも、とくに以下の質問はよくされるものなので、どれを聞かれても回答できる準備と対策が必要となります。
➀ 家賃や公共料金などの支払いが遅れているのはなぜか?
家賃や公共料金などといった毎月、定期的に支払うものに遅れや未納がある場合には、必ずその理由を聞かれます。
確認の対象となるものとしては、以下のものがあります。
| ● 家賃 ● 公共料金 ● クレジットやローンの支払い ● 携帯電話の料金 ● 住宅ローンや固定資産税の支払い |
これらの中に、支払いがなかったり、遅れている月がある場合には、それだけで融資はかなり厳しくなってしまいます。
また、確認のされる範囲は、
「 直近より6ヶ月~約1年前 」
までというのが一般的です。
確認は、引き落しのされている通帳や公共料金等の支払いの控えなどを、過去にさかのぼって確認して行います。
なので、もし、この期間内に支払いの遅れがある場合には、しばらく申込みを見合わせた方がよいかもしれません。
確認で重要となるのは「本来、納付すべき期限までに支払いがされているか?」ということです。
したがって、「申込みの時までに遅れ分をまとめて払っておく」というのは通用しません。
② 営業場所はどこなのか?
営業場所とは、事業を始める根拠となる場所であり、通常は自宅か賃貸したテナントのどちらかとなります。
この確認のために不動産屋の間取図や利用条件が記載された資料の提出を求められますが、面談の段階では必ずしも正式な賃貸契約までしている必要はありません。
なぜなら、先に契約をしてしまうと融資がダメだった場合に、それらの費用がムダになってしまうからです。そのため、日本政策金融公庫でも、融資が確定する前に賃貸契約等をしないことをすすめています。
これらの資料とともに、住宅地図のコピーや、建物外観の写真を用意しておくと好印象となります。
なお、融資の結果がでるまでにそのテナントを他に借りられてしまったり、勝手に他の物件に変更してしまうと、その融資はやり直しとなってしまいますので注意してください。
自宅を事務所として利用する場合には、その建物を利用する権限があることを証明する資料(建物の登記簿謄本など)を提出します。
ここで気をつけなければならないのが、自宅が個人名義の賃貸契約となっているにもかかわらず、法人事務所として利用するようなケースです。
この場合には、法人名義に契約を切り替える、建物大家の使用承諾を得るなどをしないと、利用条件違反となり、融資が通らないことがあります。
また、同様に賃貸借契約の利用形態が「事務所」ではなく「居宅」となっている場合にも、条件違反となることもあるため、事前に確認しておく必要があります。
③ なぜ、この事業を始めようと思ったのか?
これはほぼ必ず聞かれる質問の一つですが、ここで重要なのが「公利」という視点です。
開業の動機が単に自分の金儲けだけを考えたものではなく、多くの人に利益を与えるもの、いわゆる「公利」にもつながるという点をアピールできれば、金融機関の評価は高くなります。
【回答例】
| 「私は子供のころに、普段は不仲だった両親がたまに連れて行ってくれた外食のときには、とてもなごやかに笑顔で過ごせたため、食事にはこんな力があるんだと感動したのが飲食業にあこがれを持ったきっかけです。この経験を通して、今後は自分でおいしいものを提供するだけでなく、あの時と同じように多くの人に笑顔になってほしいという思いから飲食店を始めることにしました。 |
④ これからする事業の経験はどのくらいあるのか?
事業経験の有無は、融資の審査に大きな影響を及ぼします。
事業経験の期間は「5~6年以上」あれば問題ないといえますが、できれば「3年」以上は欲しいところです。
なお、事業経験がまったくなくとも、フランチャイズに参加してシッカリとしたトレーニングを受けていれば「事業経験あり」と認めてもらいやすくなります。
もし、事業経験が少ない場合には、
・飲食店でパート勤務などをして、実績を作ってから申し込む
・前職で経験した関連する業務(例えば、経理や仕様品管理、接客など)を組み合わせてアピールするなどの対策が有効です。
実際、私のお客さんの中でも、飲食店の勤務経験はないが、それまで勤めていたパン工場での商品の販売や製造、商品開発の経験を活かし、それらの知識を活かしたパンをメニューにして提供するというプランで、見事満額融資に成功した方がいます。
また、それまで飲食店の勤務経験はありませんでしたが、申込の半年前から知り合いの居酒屋で仕事終わりにパートとして勤務し、その実績と努力が買われて融資に成功した方もいます。
このように、直接の勤務経験がない場合でも、工夫や努力により勤務経験に代わるものとして認められることがあるため、勤務年数が少ない場合には、このような組み立てができないかも検討してみてください。
⑤ これまでに何か自分で事業をしたことはあるか?
この質問は、上の質問と同じように、一見すると過去の経験を聞いているように思えますが、これとは異なり「過去に事業主として事業をした経験があるか?」ということを確認するものです。
創業融資は、基本的にそれまでに事業経験のない方を対象とした制度です。
したがって、以前に、何らかの事業経験がある場合には、新規開業融資ではなく他の融資制度を利用しなければならないことがあります。
なお、アルバイトや社員として働いた経験は、ここでの事業経験には当たりません。
⑥ テナントを借りて営業するのか? なぜその場所で営業するのか?
前述したように、テナントを借りて営業する場合は、面談時に賃貸契約まで締結しておく必要はありません。
不動産屋の間取り図(間取りや住所、家賃、保証金の額等が記載されているもの)を提出することでもOKです。
しかし、「なぜその場所で営業するのか?」は、その後の集客や売下、事業の方向性にかかわる重要なポイント項となるため、しっかりと説得力のある回答をする必要があります。
よくある回答として
「単に家賃が手ごろだったから」とか「物件に空きが出たから」、「自分の好みにあったから」
などの解答をする方がいますが、これらはNGです。
あいまいな理由ではなく、納得できる根拠ある回答ができるようにしておきましょう。
【回答例】
| この場所は大通りからは一本奥に入った通りですが、次のようなメリットがあるためこの場所を選びました。 ➀ 大通りから見込み客を誘導できる場所である。 ➁ 近隣に同じような業種の店が少ない。 ③ 統計調査の結果から、比較的購買力の高いターゲット層が見込める。 ④ 同じような条件の他地域と比較して、家賃相場が安い。 |
⑦ 営業時間は? 定休日は?
営業時間や定休日は、売上げの計算にも直接かかわってくる項目です。
そのため、単にこれを決めたということではなく、必要な売上げ等から逆算して決めるべきものといえます。
具体的には、必要な売上げを平均来客数や平均客単価で割ることにより、おおよその必要な勤務日数や時間を決めていきます。
また、パートをシフトで利用する場合には、人件費の計算のためにも、曜日ごとのシフトなども決めておく必要があります。
【回答例】
| 平均来客数:25人 平均客単価:3,000円 売上げ目標額 25人×3,000円×24日=180万円/月 以上から、営業日は、月~土の6日間(月24日)が必要 |
⑧ 主力となる商品は何か?
サービス業や小売業などでは、
◆ 主力商品が売り上げに占める割合
◆ 仕入先
◆ 掛け率
◆ 売掛・買掛の期間(サイト)
などを事業計画書に記載する必要があります。
仕入先は、肉・魚・酒・その他のように品目ごとに決めますが、メインとなる商品については一社に絞らずに複数の候補を用意することで、不意の品切れに対応できるだけでなく、より安いところから臨機応変に仕入れることができるようになります。
もし、主力商品が決まっていない場合には、自分で想定したもので説明しますが、この場合でも相場観や本当に仕入れができるのかなどについての信ぴょう性が見られます。
具体的な方法については「日本政策金融公庫の創業計画書の成功実例を完全公開!」の記事でも解説していますので、ご参照ください。
【回答例】
| 今回、予定しているのは居酒屋なので、主力商品といったものはありませんが、客単価は2,700円程度を予定しています。この客単価の根拠としては当店メニューでいえば、 ドリンク@500円×2、メインメニュー600円×1.5、サブメニュー400円×2 といった組み合わせを想定しています。 |
⑨ 想定する月の売上げや経費の額はいくらか?
予定売上げを考える際に気をつけるべきなのは、「根拠なく右肩上がりの数字にしない」ということです。
よく毎月売上げが10%ずつ増えていく形となっているようなケースがありますが、この場合、なぜ、10%増の売上が見込めるのかの根拠がなければ、評価はされません。
また、通常、どんな商売でも季節的に売れる、売れないの変動(季節変動)やその業種特有の波がありますが、これを無視した計画は信ぴょう性の乏しいものとなってしまいます。
同じく経費についても、売上げの増減に伴って変動するのは原価率だけではないため、これらについても計画に反映させる必要があります。
売上げを作る際の注意点については、「金融機関も認めた!創業融資を引き出す売上げ計画の作り方」の記事で解説していますが、例えば、座席についても常に満席にするのではなく、死席(4人テーブルを2人で利用させる場合の2席)の発生や、曜日による回転数の増減なども想定した計算とするなどの配慮や根拠が求められます。
⑩ 取引先はどういう会社なのか?
メインとなる取引先については、その事業内容などの他に、そこからどの程度の仕入れや販売をする予定なのかを答えられるようにしておくのが望ましいです。
なお、注意しなければならないのが、その取引先が違法や非合法なことをしている会社でないということです。
もし、仮に問題がある、非合法的なことをしている会社であるということが判明した場合には、審査の上でも大きな不利となります。
すべての状況を調べるのは難しいですが、最低でもネットなどにより、その会社の評判や過去に事件を起こしていないかなどを調べておくべきです。
【回答例】
| 食材のうち、精肉については〇〇商店から約〇万円を、野菜については〇〇株式会社から約〇万円を、その他食材については〇〇物産から約〇万円を仕入れる予定です。
なお、これらの会社はいずれも創業〇年以上の企業であり、信用できる先となっています。 |
⑪ なぜ、計画通りの売り上げを達成できると思うのか?
このような質問をされた場合には、今回の開業にあたり調査・試算した結果や、過去の事業経験から計画通りの売上の確保は十分可能と考えていると説明するのが基本です。
そのためにも、その前提となる事業計画は精緻に作る必要があります
しかし、できないことや経験がないものについては無理に「できる、頑張る」などと主張するのでなく、その点については他の人材にまかす、外注するなどといった現実的なプランを考えておきましょう。
フランチャイズの場合には、本部から同程規模の店舗のデータをもらって参考にすると、内容に信ぴょう性が増します。
【回答例】
| 私は実際の経営に携わってきたことはありませんが、以前の飲食店勤務でホールと調理を担当してきたので、メニュー作成、原価計算、接客については自ら対応します。また、これまで担当した店舗の中で赤字を出したことがないことから、今回の営業についても同様に黒字化することは可能と考えています。しかし、経理については経験がないので、この点については経理の経験者を採用して対応したいと考えています。 |
⑫ もし、計画通りにいかず、返済ができなくなったらどうするつもりか?
通常は、ここまで突っ込んだ質問はあまりないのですが、以前のお客さんの例ではこのようなケースもあったので、以下を参考に事前に回答を準備しておいた方がよいでしょう。
【回答例】
| 現時点でそのようなことは考えていませんが、もし、経営がうまくいかなくなった場合には、何らかの原因があると思われるので、まずはその原因を究明し赤字になる前に対策を講じたいと考えています。
具体的には、来店者からアンケートをとり問題点の把握に努める、商品構成や価格設定を見直すなどを行う予定ですが、その際には売上げだけでなく、パートを減らして身内で対応する、広告宣伝の方法を見直すなどの経費削減もしたいと考えています。 |
⑬ 営業に必要な許認可の見通しは?
飲食店の営業の場合、保健所の営業許可と食品衛生管理者の資格が必ず必要となるので、この2点については早めに対策をしておくべきです。
しかし、保健所の営業許可は内装設備完成し、電気、水道が開通した後でないと検査を行うことができないため、この点については工事会社との調整も必要となります。
また、深夜営業をする場合には、これらとは別に「深夜酒類提供の届け出」を警察署に提出する必要があるので、これ取得の見込みについても答えられるようにしておく必要があります。
【回答例】
| 保健所の指導により、営業許可の申請は工事完了の10日までに出すこととなっているので、工事業者との調整の上、〇月〇日頃には取得できる見込みです。 |
⑭ 融資の希望額が大きすぎるのではないか?
一般的に融資希望額が1,000万円をこえる申し込みについては、融資額が大きいと判断されやすくなるため、このような質問をされる可能性があります。
融資の返済が無理なくできるかは
「経費控除後の利益+減価償却費 > 返済額」
という公式が成立している必要がありますが、そのためにはその前提となる売上げと経費が適正でなければならません。
売上げと経費は事業計画書にもとづき計算されているので、もしこのような質問をされた場合には、「この売上と経費は事業計画書にもとづき算定したものである 」、「この売上げを実現するためにはこれだけの経費が必要となる」ということを順序だてて説明します。
しかし、大きな融資を受けたいというだけで、単に売上げや経費を膨らませただけの計画ではこのようなことはできないため、しっかりした積み上げをするようにしましょう。
⑮ 信用保証協会融資(制度融資)への申込みはしているのか?
たまに、担当者から「制度融資の利用はしているのか?」と聞かれることがあります。
制度融資との併用自体については問題ないのですが、これを伝えるとそちらの状況をいろいろと聞かれる可能性があるので、このような場合には下記の回答例のように話していただくのがよいと思います。
【回答例】
| 現時点では制度融資の申込みは考えていませんが、今回の申込みで不足が出る場合には補充的に、制度融資の利用も検討したいと考えています。 |
以上が、主な面談時での質問例とその回答となります。
これらのすべての質問がされるわけではありませんが、いずれも十分に聞かれる可能性があるものなので、シッカリと頭に入れて面談に望んでいただきたいと思います。
「自己資金」に関する質問は、なくなったのか?
日本政策金融公庫の「新創業融資制度」は2024年3月で廃止され、これに伴い「新規開業資金」の制度へとリニューアルされました。
そのため、申込要件からは、これまで必要だった「1/10以上の自己資金の保有」は不要となりました。
そのため、以前ほど自己資金に関する質問がされることはなくなりましたが、それでも自己資金がある場合には、以前と同様にその出所や貯めた経緯などについて確認が行われます。
自己資金の確認は
➀ 実際に事業で使用している通帳(法人の場合は、法人名義の通帳)
➁ 事業の元手が入っている個人の通帳
の2点で行われるので、自己資金の要件がなくなったから質問もないとは考えずに、最低限の準備をしておく必要があります。
まとめ
以上のように、金融機関との面談で質問される項目はほぼ決まったものとなっています。
とくに次の項目については、聞かれる可能性が高いと思ってください。
| 面談で聞かれる可能性の高い質問 ✔ 家賃や公共料金の支払い遅れや未納の有無 ✔ 開業の理由と事業の経験 ✔ テナントの利用予定や契約内容 ✔ 売り上げの見込みとその根拠 |
なお、日本政策金融公庫の面談は提出した事業計画書の内容に沿って行われるため、いい加減な計画内容では面談でそれを指摘されたときにうまく対応できなくなってしまいます。
そのため、事業計画書の内容をキチンと理解し、頭に入れておくのは当然ですが、経験のある第三者や専門家のアドハイスを受けることで、計画内容の見直しや面談での注意点を見つけることができます。
119番資金調達NETでは、事業計画書の作成の他、許認可申請の代行を割安な金額でお手伝いしています。
また、このブログではご紹介していないテクニックや注意点についても、直接、その方の状況にあわせてアドバイスしています。
随時、初回の相談無料でご利用いただけますので、お気軽にご相談ください。
※ こちらから電話できます。