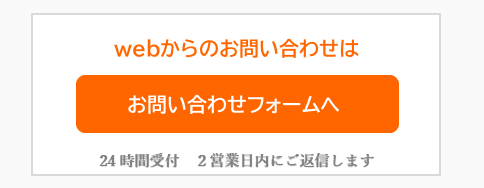日本政策金融公庫の「新規開業・スタートアップ支援資金」は、これまでの新創業融資に代わり、自己資金なしで無担保無保証の融資が利用できる融資として注目されています。
しかし、119番資金調達NETが独自に確認したところ、自己資金なしでも申し込めるというのはあくまでも制度の上でのことであり、実際の融資では自己資金がない申し込みは厳しいという回答を得ました。
そこでこの記事では、「新規開業・スタートアップ支援資金」における自己資金の必要性や自己資金に関する正しい知識について解説いたします。
「新規開業・スタートアップ支援資金」と自己資金について
「新規開業・スタートアップ支援資金」とは?
「新規開業・スタートアップ支援資金」は、日本政策金融公庫の創業者向け融資の一つで、2024年4月にそれまでの新創業融資制度に代わって開始されました。
詳細については「公庫担当者から聞いた。「新規開業支援資金」の80%の人が知らないこと。」でご紹介していますが、主に次のような特徴があります。
● 無担保・無保証人融資で融資が利用できる
● 融資の利率が一律0.65%引下げられる
● 長期での返済が可能
● 自己資金が不要で申し込める
| 新規開業・スタートアップ | 新創業融資 | |
| 融資限度額 | 7,200万円(運転資金4,800万円) | 3,000万円(運転資金1,500万円) |
| 返済期間 | 設備資金 20年以内 運転資金10年以内 | 各融資制度に定める返済期間以内 |
| 利率 | 基準金利 ※創業者は0,65%引下げ | 基準金利 |
| 担保・保証 | 不要 | 不要 |
| 自己資金 | 不要 | 創業にかかる経費の1/10以上必要 |
「新規開業・スタートアップ支援資金」で、なぜ、自己資金が必要なのか?
「新規開業・スタートアップ支援融資」は、自己資金不要で利用することができますが、自己資金の審査が行われないわけではありません。
また、自己資金がある場合とない場合とでは、審査に与える影響も大きく異なります。
119NETで確認したところ、日本政策金融公庫の担当者から以下のような回答がありました。
ℚ 新制度も自己資金の有無の確認は行われるのか?
「制度としての自己資金要件はなくなったが、自己資金がある方が有利になるのはこれまでと同じであって、その判断をするためにも、自己資金の有無は確認する」
ℚ 新制度でも自己資金は必要なのか?
「自己資金は
・これまでに資金をためてきた努力や経緯
・これがない場合、結果的に融資額が大きくなる分だけ返済が困難になる
という2点において、融資審査でもその有無は重要なポイントなる。
したがって、自己資金がまったくない申し込みは、かなり難しいものになる可能性が高い」
このように「新規開業・スタートアップ支援融資」は、自己資金不要で申し込むことができますが、十分な額の融資を獲得するためには、ある程度の自己資金は不可欠ということになります。
そのため以下では、「新規開業・スタートアップ支援融資」においても、自己資金は必要であるということを前提に、自己資金について解説していきます。
自己資金について
自己資金を準備するには、「そもそも自己資金とは何か?」や「どんなものが自己資金になるのか?」を正確に理解しておく必要があります。
自己資金とは
「自己資金」とは、これから始める事業に使うために自分で貯めた預貯金等のことをいいます。
したがって、いくら通帳に残高があったとしても、それが事業に使う資金でない場合は、自己資金とはなりません。
日本政策金融公庫や信用保証協会では、自己資金の確認は資金の入っている通帳の以前の履歴を見て判断しています。(具体的には半年~1年前程度までさかのぼって確認)
そのため、その出所に問題がある場合や不審な点がある場合には、自己資金として認められないことがあります。
自己資金として認められるもの・認められないもの
通常、以下のような資金は、自己資金として認められます。
自己資金として認められるもの
| ◆ コツコツ貯めたお金でその経緯が通帳でわかるもの ◆ 退職金や生命保険の解約金など、その出所がハッキリしているお金 ◆ 親などからもらったお金 ◆ 自分の資産を売却して、その経緯がわかるお金 ◆ 相続により得たお金 ◆ 会社の場合の資本金 など |
しかし、次のようなものは自己資金と認められません。
自己資金として認められないもの
| ◆ 自分で現金で貯めたお金(俗にいう、タンス預金) ◆ 通帳に入金されていてもその出所を説明できないお金 ◆ 親や他人から借りたお金 ◆ 他から融資されたお金 ◆ 法人設立のために支出した費用 |
もらったお金や借りたお金は自己資金になる?
自己資金として認められるかどうかのポイントは
「出どころのわかるお金であるか、どうか?」
ということにあります。
上の例で、タンス預金や入金された経緯がわからない資金が自己資金とならないのは、その出所や入金の経緯を説明できないからです。
また、同じく上の例の「親などからもらったお金」は自己資金として認められるのに、「親などから借りたお金」が自己資金とならないのは、前者は返金義務がないのに対して、後者は融資と同じく返済しなければならない資金だからです。
なお、これらの判断の基準は日本政策金融公庫のものとなりますが、信用保証協会の融資ではに異なることがありますので、詳しくは「東京信用保証協会の融資希望者必見!どこにも書かれていない重要ポイント」の記事をご参照ください。
自己資金に関する間違った噂に注意
自己資金については、ネットなどでいろいろな噂がされていることがありますが、これらの多くは何の根拠もないものだったりします。
そこで、ここではこのような噂のいくつかを取り上げ、それに対する正しい考え方を記載しましたので、融資申込みの際の参考にしてください。
① 見せ金について
「はじめにある程度の見せ金を用意できれば、これをもとにして日本政策金融公庫からその数倍の融資がうけられる。また、さらに、この融資を自己資金にすることにより、さらに信用保証協会付融資を受けることができる。 」
【✕】
そもそも、融資を受けたお金はあくまで借入金であって、これを自己資金とすることはできません。また、「見せ金」は通帳の動きを見られればすぐにわかってしまいます。
② 親兄弟から借りたお金
「親や兄弟から借りたお金は自己資金となる」
【✕】
たとえ、親兄弟から借りたものであっても、返済義務のあるお金は自己資金とはなりません。
ただし、それが贈与されたものである場合には、自己資金とすることができますが、審査ではそれを証明する資料の提出や確認がされることがあります。
③ 開業前に支払った経費
「開業前に支払った経費がある場合、これらはすべて自己資金の一部としてカウントすることができる」
【✕】
開業前に使った費用のうち、
・「事業に関して申込前に支払ったお金(先払いした家賃など)」
・「その支出を証明できるものがある」
この2点を満たすものについては自己資金として認められます。
しかし、事業に直接関係ない支出や、領収書がないもの等については、自己資金と認められないことがあります。
なお、創業時の法人設立登記の費用については、原則として自己資金とは認められません。
④ 自己資金の不足の場合
「創業融資を利用する場合には、自己資金がなくとも、事業計画の内容がよければ、融資の対象となる」
【△】
以前の新創業融資では、1/10以上の自己資金なければ、融資を申し込むことができませんでした。
これに対して新たな「新規開業・スタートアップ支援融資」は自己資金の要件がないため、これがなくとも申し込みはできますが、実際にはまったく自己資金がないような場合には、あまり大きな金額は見込めない可能性があります。
➄ 法人の資本金
「法人で創業融資の申込みを行う場合、登記簿謄本に記載された資本金の額を自己資金として認めてもらえる」
【✕】
法人を設立して融資の申込んだ場合でも、「資本金の額」=「自己資金」となるわけではありません。
このような場合でも「どうやってその資本金を貯めたのか?」といった確認は通常の場合と同じように行われます。
⑥ 2つの創業融資の併用
「日本政策金融公庫と信用保証協会の融資(制度融資)を同時に申し込むことができる」
【〇】
日本政策金融公庫の融資と制度融資は別の融資制度のため、これらは同時に申し込むことができますが、その際には利用目的(特に設備資金)が重複しないようにする必要があります。
同時申し込みの詳細については、「実は簡単!日本政策金融公庫と信用保証協会融資を同時に獲得する方法」の記事をご参照ください。
合法的にできる「自己資金」の増加法
これまでの説明で、「自己資金がいるのか?いらないのか?」や「どんなものが自己資金になるのか?」がおわかりいただけたと思います。
しかし、これから創業する方の中には「自己資金が少ないので不安」という方や、「できれば、もっと自己資金を増やして申し込みたい」という方もいるかと思います。
そこで、ここではそんな方のために「合法的に自己資金を増やす方法」をいくつかご紹介します。
1.会社を作って出資者を集める。
現在は、一人だけで会社を立ち上げる方が増えていますが、これだけでは思うように資金が集められない場合も少なくありません。
なのでこのような場合には、一人からの金額は大きくなくとも「できるだけ多くの人から出資を集める」ということが資本金集めの基本となります。
また、現在の会社法では、種類株を活用することで
● 出資額は少なくとも経営権を確保する
● 配当に優先順位をつける
などの設計もできるので、これをうまく利用すれば、出資額に関係なく安定した経営権を確保することができます。
2. 「現物出資」を併用する。
会社の設立する時に資本金にすることができるのは、金銭だけではありません。
自動車や什器といった、発起人個人の財産などでも出資することもできます
このような出資の方法を「現物出資」といいます。
この方法を利用すれば、預金にそれらの財産を加えて、さらに自己資金を大きくすることができます。
詳細な手続きについてはここでは省きますが、現物出資を利用するときには
◆ 会社の設立時にしかできないこと。
◆ 設立時の定款に現物出資の内容が記載されていること。
◆ 現物出資の評価は、時価相場と同程度の額であること。
◆ 現物出資だけでなく、すぐに使える資金も用意できていること。
などに気をつける必要があります。
3.事業開始前に支払った費用を自己資金とする(「みなし自己資」の活用)
現物出資の方法は、手っ取り早く自己資金の額を増やすにはいいのですが、
「設立時にしか使えない」、「大きな金額にしにくい」、「個人事業では使えない」
などといった制約があります。
そこで、自己資金を増やす最後の手段が「みなし自己資金」の活用です。
この「みなし自己資金」とは
「融資申込前までに事業のために使った費用は、これも自己資金として認める。」
というものです。
具体的には以下のものが該当します。
みなし自己資金として認められるものの例
◆ 事業の開始前に支払った原材料の代金やHPの作成料
◆ テナントの契約にかかった手付金や、先行して行った内装の費用
◆ その他の事業開始前に支払った事業に関する支出
みなし自己資金として認められないものの例
◆ 会社の設立にかかった費用(定款認証代、印紙代、登録免許税、専門家に対する報酬)
◆ 事業との関連性か薄い支出(打ち合わせのた目の食事代や接待費)
◆ 支出から長時間が経過し、事業との関連性が認めにくいもの
なお、「事業の経費を先に払って、通帳の残高が減ってしまったら、その分自己資金も減るのでは?」と心配される方もいますが、これらの先払いした費用が事業に関するものならば、その部分も自己資金として認められるので大丈夫です。
例
Q:1ケ月前の自己資金額は500万円だったが、先に事業の経費を300万円支払った。
この場合、通帳の残高200万円だけが自己資金になるのか?
A:現在の残高200万円+事前に支払った経費300万円(みなし自己資金)=500万円が自己資金として認めてもらえる。
ただし、これらを自己資金として認めてもらうためには、支払ったものの領収書(領収書が出ないものについては支払いを控えたメモ)が必要となります
また、以上は日本政策金融公庫の融資の場合の話となりますが、制度融資の場合では、それを主宰する都道府県や市町村により自己資金として認められる対象や範囲が異なりますので、ご注意ください。
自己資金に関するこんな事例
自己資金に関していくつか変わった事例がありますので、ご紹介します。
事例1 金のかたまり → 〇
以前に私のお客さんで、自分の知り合いから開業祝いとして金の塊をもらった方がいました。
これが自己資金にできるかについて公庫に確認したところ「正規の貴金属商で鑑定したもらった証明と、直近での相場価格がわかる資料があれば自己資金として認める」との回答がなされました。
事例2 休眠会社の売買 → ✕
以前、お客さんの知り合いに、自己資金を大きく見せようと考え、休眠中の会社を買い取り、商号や本店、役員をすべて入れ替えて融資の申込みをするというケースがありました。
しかし、公庫ではその過去の登記簿を取り寄せて確認しただけでなく、途中の期間についての決算書の提出を求めたため、実質的な自己資金がないことがわかり、申し込みは失敗に終わりました。
事例3 タンス預金の預け替え → ✕(場合によっては〇のケースも)
500円玉貯金がまとまった額となったので、これを自己資金にしたいと考えた方がいましたが、このようなタンス預金は自己資金として認められません。
そこで彼はそのお金を一時的に定期にし、これを解約したものを自己資金として利用しようとしました。アイデア的にはなかなかよかったのですが、「定期として預けた期間が短すぎる」という理由で、結果的には自己資金と認めてもらえませんでした。
しかし、このようなタンス預金でも最低1年以上預金または定期に入れて預けておけば、これを自己資金として認めてもらえる場合があります。
事例4 母親からもらったお金 → 本来は〇
以前のお客さんの中に、開業の支援金として母親から150万円の資金の贈与を受けた方がいました。
本来であれば、このような資金は自己資金の一部として認められるのですが、その方はうっかり、現金でもらったものを自分の口座に入金してしまいました。
その結果、母親からもらった資金であるということを証明できなくなってしまい、自己資金としても認められませんでした。
まとめ
「新規開業・スタートアップ支援融資」では、自己資金は不要とされていますが、実際に希望額の融資を受けるには、その額に見合った自己資金が必要となります。
自己資金は通知用にに資金が入っていればよいというだけではなく、その出どころや貯めた経緯も慎重に調査されるため、シッカリと準備しておくことが重要となります。
もし、自分の自己資金に不安がある場合には、日本政策金融公庫や専門家にあらかじめ確認してもらうことをお勧めします。
119番資金調達NETでは、事業計画書の作成や資金調達全般に関するサポートの他、このブログではご紹介していないテクニックや融資で注意すべき点についても、その方の状況にあわせてアドバイスしています。
随時、初回は相談無料でご利用いただけますので、お気軽にご相談ください。
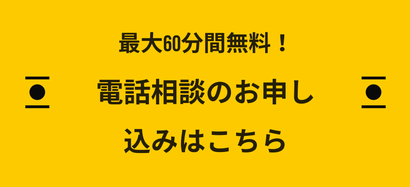
※ こちらから電話できます。